Blog /ブログ
朝日新聞にてグリーンラッピングをご紹介頂きました!
03.14
3月5日付朝日新聞eco活プラス面にて、プレゼント・ツリーの長年の支援者であ
る、そごう・西武さんのグリーンラッピングの取組みがご紹介されました。
詳細はこちら。
そごう・西武では2009年から、贈答シーンにエコ活動を載せた「グリーンラッピング」
を展開しています。
ギフト包装を「グリーンラッピング」でご依頼いただくと、100円でリーフ型の
チャームをご購入、そのうち50円がPresent Treeに寄附されるしくみです。
09年に始めて、今年でちょうど10年。
息長い活動により、今までに北海道、山梨県、千葉県、宮崎県、熊本県、岩手県
のプレゼント・ツリーの森に、計13,420本の樹を植え、育てて頂いており、毎年
同社労働組合の皆様が森の活動に参加、各地との交流を続け、森だけでなく地域
丸ごと元気にしてくださっています。
皆様も、グリーンラッピングでのギフトはいかがですか?
初の試み!indoor里山!
02.27
「里山の再生~有効活用の必要性」の普及啓発のため、里山に眠ったまま忘れ去られている「在来種の種=シードバンク」から育てたグリーンを、様々なシーンで置いて頂く意義についてご説明させて頂いています。
そのような中、よくご相談を受けるのが「室内で観葉植物替わりに置けますか?」というもの。従来は、ずっと「室内はお勧めしません」とお応えしていたのですが、、、、
企業や団体での「ミニ里山BONSAIづくり」のワークショップが回を重ねる内に、ご自身の創った小さな里山をデスクの上で育てる方が増えており、その里山BONSAI達がどれも立派に美しく育っているのを見るに付け、「時々外に出して光と風に当てれば大丈夫かも」との認識に至りました。
写真:左)当社の会議テーブルの里山BONSAI、右)ワークショップの様子、下)約1年半デスクで育ったミニ里山
そこで、本格的な実験へのご協力に名乗りを上げて下さったのが、京橋は東京スクエアガーデン6階の「シティラボ東京」さん。「indoor里山」を設置させて頂き、室内環境でもしっかり育つのか?実験中です!
この実験は、ランドスケープデザインや都市・建築のサステイナビリティに関するコンサルティングで有名な(株)ヴォンエルフの取締役、永積 紀子さんに御指導頂きながら進めております。
8月に設置し始めて約半年が経とうとしていますが、今のところ大きな問題点は無さそうで、シティラボ東京のアーバニストの皆様の心のこもったお世話により、とてもすくすく育っています。
写真:シティラボ東京でのindoor里山の様子
オフィスワーカーの生産性向上と、心身の健康への配慮は喫緊の課題であり、様々な調査データの裏付けにより、オフィス空間の質が労働の質を左右するといわれ始めています。そのような中、オフィスにおける「バイオフィリックデザイン※」への期待が高まっています。
人の健康やウェルビーイングと執務空間との関係を規定する第三者評価制度であるWELL Building Standard(WELL)でも、心の健康を向上させるためのバイオフィリックデザインが評価に含まれています。
indoor里山は、室内のバイオフィリックデザインに、我々日本人が古くから慣れ親しんだ日本の里山に自生するトレーサビリティが確保された苗と、国産材による器を取り入れるものです。さらに、オフィスワーカーと里山保全活動を繋げることで、環境保全と健康の向上に寄与します。WELLでは、寛大な行動やボランティア活動が、健康とウェルネスに好影響をもたらすと結論付けており、「こころ」の評価のカテゴリーの加点項目96「利他的行為」では、ボランティア活動への参加や慈善団体への寄付を評価しています。
さらに、このindoor里山は、室内のバイオフィリアと、里山保全活動を合わせてご提案することで、SDGsへの取り組みも応援します。
お近くにお越しの際には、是非シティラボ東京にお立ち寄り下さい。
※バイオフィリック・デザインとは、自然を感じられる環境を、建築やインテリアで再現する取り組みのこと
写真:上)シティラボ東京・アーバニストの方と打合わせするアーバン・シードバンク事務局・石森
下)ヒサカキにカイガラムシが付いてしまったため一部入れ替え
北海道で、新しいPresentTreeがスタート
10.26
お待たせいたしました!北海道で、新しいPresentTreeがスタートしました。
北海道のプレゼントツリーはずっと人気で、毎年すぐに満員になってしまい、今年もずっと受け入れを中止しておりましたが、やっと再開できます。
今回の場所は、大自然が拡がる中川郡中川町。エゾシカやキタキツネ、オジロワシ、、、沢山の生きものたちに遭遇する町です。
毎年秋には町民参加による植樹祭が行われており、これに参加させて頂きつつ、併せて「プレゼントツリーin中川」の協定締結式を実施して参りました。
PresentTreeが目指しているのは「新しい林業」です。木を切って材として売って商売にするだけでなく、「そこに自分の記念の樹があるから、人々がその地を訪れ、地域を豊かにしていく」という森の新たな活用法を目指しています。
100年後、日本の人口は三分の一になると言われています。そのときに、森はどうなるのか?私たちはそれを本気で心配しています。
基本的に、人・物・金・情報が上手く循環し続けてさえいれば、国や地域の活力は衰えないと思います。他のどの国よりも急速に少子高齢化が進み人口減少の道を辿る日本、どの国よりも個人の現預金比率が高い日本が、世界のモデルとなるべく「活力ある未来社会」を実現するため、如何に「人とお金を循環させていくか?」のビジネスモデルの社会実験として、プレゼント・ツリーを展開しています。
ゆえに、各地のPresentTreeでは、拡大造林時代の前の時代の森を復活させるお手伝いをしています。人の手がかかりすぎないように、です。そうすると広葉樹が主体の森づくりになります。
中川町では、広葉樹主体の林業を脈々と続けてこられ、その価値を高めるための「新たな林業」を模索しているとお聞きし、更に200年先の林業を本気で考えていると伺い、これはPresentTreeとしてお手伝いのし甲斐があるな、正にPresentTreeが目指す所そのものだな、と、協定を決めました。
プレゼント・ツリーの森、ひとまずは10年御当地とお付き合いし続けるのが最たる特徴です。200年までまだまだですが、今後10年間、中川町でのプレゼントツリーの森づくりが続きます。
皆様、どしどしご参加ください。植樹イベントは来年の秋です。乞う御期待!
第15期の活動報告に代えて
07.14
認定NPO法人環境リレーションズ研究所は、お陰様をもちまして15期という節目の決算を完了しました。ひとえに、皆様方のご尽力の賜物と有難く厚く御礼申し上げます。
中核事業であるPresentTreeは、
1.中々動かない圧倒的多数「=一般生活者」をエコアクションに引っ張り込むインフラ
2.成熟社会における地方創生の在り方
の2点を目論み、他のどの国よりも急速に少子高齢化が進み、どの国よりも個人の現預金比率が高い日本が、世界のモデルとなるべく「活力ある未来社会」を実現するために、如何に「人とお金を偏在させずに循環させていくか?」の一つの社会実験として進めてまいりました。
認定NPO法人環境リレーションズ研究所で、この社会実験を担いムーブメントの素地を創り、上手くいったスキームを企業や団体の皆様の本業の中で活用頂くことを株式会社環境ビジネスエージェンシーでお手伝いしつつ、持続可能な環境施策を生み出し続けること、それが、私共のミッションです。この営利と非営利組織との両輪運営こそが強みだと、対外的にも訴求し始めてから12年目を迎え、やっとその意味が浸透して参りました。
10年間存続できる企業は約5%といわれますから、それなりに存在意義のある組織で在り、活動なのだと自認する一方、企業の寿命は30年といわれる中、30年後に残るために今何をすべきか?を模索し続けている昨今です。
首都圏のヒト達を各地方の森に植えた苗木の里親として、当地との10年間の交流を育み、森だけではなく地域丸ごと元気にしていく、という仕組みは、2005年1月スタート来順調に広がり続け、2011年の3.11発災直後は、長年の地域振興実績と相俟って、被災各地からの活動誘致が続き、2012年度の岩手県宮古市をはじめとし、2014年度に宮城県大崎市、2015年度に福島県広野町におけるPresentTreeが実現、被災三県における交流の森づくりは、お陰様をもちまして当初協定面積への植栽を前期にはほぼ完了、当期には面積の拡大、付随事業の展開などに発展中です。特に、当期まで3カ年に亘り蒔いた施策の種である「ふくしま環境・リサイクル関連産業研究会」における浜通りの復興に繋がる事業化支援は、PresentTreeを通じた地元ネットワークが生かされ、来期には実を結ぼうとしています。
震災復興7年間で未だ7万人超が避難しているといわれているにも拘わらず、また、帰還困難区域においては、これからやっと除染が始まるというタイミングであるにも拘わらず、震災の事実は風化の一途を辿る中、PresentTreeの支援者の皆様が継続的に被災地の森づくりに足を運び続けること、その御縁が地域経済振興に寄与する事業化に繋がること、が地元からは大変期待されています。
一方、被災地以外でも少子高齢化が深刻化する地域でのニーズが根強く、引き続き「国づくり」の精神でPresentTreeを推し進めますので、ご協力をお願い申し上げます。
また、PresentTreeの森づくりの中で見えてきた新たな課題を解決するための、次の事業として立ち上げた”アーバン・シード・バンク” プロジェクトは、前々期にグッドライフアワード・環境大臣特別賞を受賞、そのお陰で当期はTBSの「EARTH Lab~次の100年を考える~」にてご紹介頂きました。全国各地の放置荒廃里山を再生するため、真っ暗な里山に未利用資源として眠り続けている休眠埋土種子(シードバンク)から苗を育て、都市の緑化に使うことで、都市の生物多様性を向上させ、里山に人と資金を流す仕組みである”アーバン・シード・バンク” も、これからの日本の発展のためのソリューションとして機能させて参りますので、併せて皆様からの変わらぬご厚誼をお願い申し上げます。
以下、活動報告に代えて決算のポイントを申し添えます。(別添:認定NPO法人環境リレーションズ研究所 過去10期対比財務諸表 参照)
1.経常収入について
1)経常収入の内訳については次のとおりです。
| 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
| 会費入会金収入 | 0.29% | 0.13% | 0.11% | 0.14% | 0.24% | 0.04% |
| 寄附金収入 | 57.91% | 68.76% | 84.02% | 74.54% | 72.49% | 79.09% |
| 補助金等収入 | 17.38% | 15.20% | 6.81% | 7.71% | 12.85% | 10.81% |
| 事業収入 | 24.41% | 15.61% | 9.04% | 17.60% | 14.37% | 10.06% |
| 受取利息(その他収益) | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.0% | 0.00% |
| 雑収入(その他収益) | 0.00% | 0.29% | 0.02% | 0.01% | 0.04% | 0.00% |
| 計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2) 仕掛事業費の計上がNPO法人会計基準に馴染まないと判断された為、前期に会計方針を変更、10年間プロジェクトであるPresentTreeの支出が事業開始~3年目迄に偏るため経常減額となりましたが、10年間のストックにより活動費用が充てられています。
2.新年度の方針
2014年度、2015年度と、大口のご支援により順調に活動を拡げてまいりましたが、そこ迄で完結してしまったプロジェクトをカバーする取組みが適わず、今期も前期同様、事業ボリューム全体が2013年度並みに留まりました。引き続き、植栽地のバラエティを整えることにより、なんとか元に戻したいと思っております。また、PresentTreeの次の一手を探しておられる支援者の方々には、”アーバン・シード・バンク”による里山再生、生物多様性保全へのご協力をお願い申し上げます。 当所はこれからも、持続的な活動の拡がりのため、非営利活動と営利活動とをしっかりと両立して参ります。また、2015年1月スタートから、順番に償還期限(協定期間満了)を迎えるエリアが増えており、その後の維持存続の在り方については、それぞれの事情・背景に応じた丁寧な対応で臨んでおります。その結果、今現在は恙なく期限を迎えることができ、新年度も細やかな対応を心掛けたいと思っております。
以上
全国学生環境ビジネスコンテスト(emFactory)
10.26
週末、六本木ヒルズ・ヒルズカフェで開催された「大学生による環境ビジネスアイディアコンテストin 企業と環境展2017(みなと環境にやさしい事業者会議主催)」で学生達のプレゼンを聞いた。
2014年から4回連続で審査させて頂いているが、今年は粒ぞろい。台風の最中にも拘わらず参加する強者たちは兎に角プレゼンが上手くてびっくり。それもそのはず、本家本元の「全国学生環境ビジネスコンテスト」=emFactory2017の運営幹部や受賞者達だった。
2004年、早稲田大学環境NPO「ロドリゲス」が立ち上げたem factoryは、来年15周年を迎える老舗イベントである。
「どうして地球のために、みんなのためになることをしているのにお金がもらえないのか?」という素朴な疑問に絆された私は、以後ずっと陰に日向に支援し続けている。その贔屓目抜きにしても、現役学生がビジネスアイディアコンテストの運営をシステム化して、毎年世代交代しながら15年も続けていることに感嘆している。
残念ながらここ数年は、ソーシャルビジネス全般に幅広く興味が分散するという広く社会的な傾向を反映し、環境に特化したビジネスコンテストへの参加者は減ってしまっているものの、脈々と受け継がれる「EcoなMoneyを作り出すfactory(名前の由来)を構想する人材づくり」は、健全だ。
今年は、「大学生による環境ビジネスアイディアコンテストin 企業と環境展」では「自転車ロードサービス」が、「全国学生環境ビジネスコンテスト」では「静脈と動脈を繋げるソフトビジネス」が、それぞれ優勝。守秘義務があるためアイディアの中身を詳細に記せないのが歯がゆいが、大変ユニークなビジネスモデルだった。
さて、どうせなら15周年イベントもこの勢いでお手伝いしようと企んでいる。2020の東京五輪に向けたCSVネタを、学生ならでは!の視点で構想してもらおう。
東京五輪における持続可能性配慮施策の課題
09.26
東京2020大会まであと3年を切ってしまいました。
サスティナブル・ビジネス・ウィメン、SUSPON、日本自然エネルギー財団で進めている、五輪の持続可能性への取り組みを後押しするイベントは、昨年12月の第一弾「小池百合子都知事への公開ブリーフィング」、今年2月の第二弾「SDGs”持続可能な生産消費”の具体化~五輪の調達を好機に!~」に続き、今月14日に「2020 SDGs東京五輪「持続可能性運営計画第2版」に向けて、企業との情報共有」を開催、その時の様子を公開致しました。
企業の皆様、メディアの皆様を中心に、120名キャパの会場に202名超ものご来場で立ち見も出る始末に、運営側は嬉しい悲鳴を上げておりました。
公務のため小池都知事は遅れるわ、講演途中でPCがフリーズするわ、で事務方はハラハラし通しでしたが、終了後、多くの記者の方々から「テーマが濃くて、食いついてしまいました。」と、お褒めの言葉を頂戴しました。
私もこの動画をスマホ&イヤホンで電車に乗りながら見ていたら、思わず吹き出してしまうような場面が多数!食いつきすぎに要注意です?!(^^;)
とどのつまりは、環境・持続可能性配慮施策のプライオリティが低く、その為元々足りていない予算が更に廻されにくくなっていること、その予算を工夫して集めようとしても商業五輪ルールに阻まれ柔軟な動きが取れないこと、それを理由に情報がなかなか公開されず、一部の関係者だけで準備が進められており、国民が置き去りにされていること、が2020大会の最たる課題です。
さあ、皆で知恵の出し処です。日本ならでは!の東京2020モデルをご一緒に創りましょう!
復興五輪のススメ
08.18
東日本大震災の被災者支援プロジェクト「JKSK結結プロジェクト」が、東京新聞への連載を通じて被災地復興の様子を伝える「東北復興日記」。2012年8月10日に連載開始してから5年目、225回目となる8月15日号に「復興五輪」について寄稿致しました。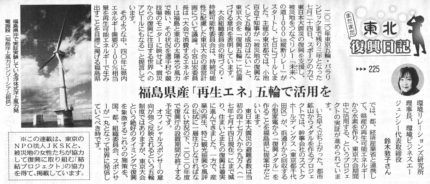
http://jksk.jp/j/yyp/tokyo_np225_170815.pdf
元々が息長い活動にならざるを得ない森林再生事業を営んでいる当社&当NPOとしては、やはりどうしても長期に亘る東北復興事業をお手伝いできないか?との思いで、復興支援型PresentTreeをはじめとする継続的な東北被災地振興に携わっており、東京新聞、そして結結プロジェクトのこの長期連載には、強く共感すると同時に、心より敬意を表します!
さて、寄稿の話に戻ります、、、
現在、その機能の存続の在り方について検討中とのことですが、2011年12月に設置された復興庁は、復興庁設置法に基づき、ひとまず2020年度末に廃止することが決まっています。
東日本大震災の避難者数は当初の五分の一程度にまで減り、住まいとまちの復興は着実に進んできた一方で、産業の再生、特に観光振興や風評の払拭に一層注力しなければならないのが今後のステージです。
そのような中、小池百合子都知事や、2020年五輪の持続可能性配慮施策を審議する街づくり・持続可能性委員会の小宮山宏委員長は、「復興五輪」を謳い続けています。
東京大会という絶好のタイミングで、是非とも「復興五輪」を象徴する施策を実践し、世界に発信していくべき時です。
みなさまも、是非応援して下さい!
五輪を契機に、持続可能な社会づくりに向けて企業ができること
03.07
オリパラ2020大会まであと3年あまり。
昨年12月4日の第一弾「小池百合子都知事への公開ブリーフィング」に続く、五輪の持続可能性への取り組みを後押しするイベント第二弾「SDGs「持続可能な生産消費」の具体化~五輪の調達を好機に!~」が開催されました。
2020大会スポンサーをはじめとする企業のCSR担当者達を中心に、当日は総勢219名の参加となり大盛況!持続可能性配慮に向けた取り組みに関する関心の高さに、主催者一同嬉しさと頼もしさを実感いたしました。
当日のアンケートでも、9割の方々が「参考になった」と評価。
「オリンピックを契機にSDGsに取り組む意義を理解できた。」「SDGsの捉え方、企業内での展開の仕方を考えるヒントになりました。」「企業側としては色んな声を上げていきたいと思いました。」
という前向きな意見や感想も多かった反面、
「大会の準備に不安を感じる。責任の所在がはっきりしていない気がする。」「実際のオリパラの調達、その結果や内容が不透明であると思いました。」「オリンピックまで時間が無いので、もう新しいことは何も決められないのではないか」
など、懸念の声も。
「東京2020競技大会・持続可能性に配慮した運営計画」第一版は、 残念ながら具体性に欠けています。今年5月までに中身が詰められると言われている第二版が、具体的な数値目標などを掲げる予定であり、その内容の作り込みが極めて大切になります。
企業の皆様へ。
企業活動の一環としてSDGsの取り組み、中でもターゲット12「持続可能な生産と消費の確保」は産業界・企業が中心的な役割りを期待されていますので、これをドシドシ押し進めて下さい。それが、世の中に大きなプレッシャーを与えることとなります。
そして、運営計画第2版を中身の濃いものとするために、2020大会で「負のレガシー」を残さないために、組織委員会や東京都、国だけに任せておくのでは無く、企業の皆様も是非「オリパラ2020で、SDGsの取り組みをしっかりやって欲しい!」と声を上げて頂きたいと思います。
※当日までに参加者から頂いた質問についての回答はこちらに掲載しております。
小池百合子都知事への公開ブリーフィング
12.05
オリパラ2020における環境・持続可能性への取組みは全く進んでいません。その現状を憂う声が多方面から集まっているので、「環境先進都市」を標榜する小池百合子都知事にエンジンを掛けて頂くための公開ブリーフィングを、関係各位結集の上実施しました。http://www.renewable-ei.org/activities/events_20161204.php
東京2020オリンピック・パラリンピックは、長年我が国が積み上げてきたサスティナブルな知恵と技を結集し、成熟国家・都市としての五輪の在り方を広く世界に発信すべき時です。しかしながら、開催まで4年を切る中、街づくり・持続可能性委員会からの提言をはじめとする環境配慮対策は一向に進む気配を見せず、各方面から焦りの声が聞こえてきます。
そこで、我々サスティナブル・ビジネス・ウィメンとしては、その焦りの声の主達に「我らが生みの親である小池都知事は、本気で環境最先端都市としての五輪を目指しているのだから、懸念される現状についてしっかり共有する場を設けるべき」と提案し、実現したのがこの公開ブリーフィングです。
2020年大会の準備については、会場の位置決定や経費削減について、IOCを含めた4者協議の下、小池知事のリーダーシップもあって迅速に進みつつあります。ようやく、「オリンピックアジェンダ2020」に掲げられている「オリンピック競技大会のすべての側面に持続可能性を導入する」という工程に差し掛かってきと言えましょう。
オリンピックの競技関係の経費は相当に合理化がなされてきたと承知しており、1都民・国民として、とても嬉しく頼もしい限りです。
ややもすると、環境対策の経費は、お飾り扱いされて削られてしまいがちですが、オリンピック憲章では、持続可能性は手段では無く目的とされています。全体の無駄遣いが削減されつつある中、ようやく、その目的達成の十分な可能性が出てきたのではないか、と知事を支持してきた私どもサスティナブル・ビジネス・ウィメンとして、大いに期待をしております。
今年8月にパブコメが終了した、「東京2020競技大会・持続可能性に配慮した運営計画」第一版(案)は、今のところ残念ながら具体性はありません。これを受け、来年前半に準備が進むと思われる第二版が、具体的な目標などを掲げる予定であり、その内容の作り込みが極めて大切になっています。
計画は、組織委員会が作成するものですが、東京都や政府もその実行の責任ある主体とされています。また、組織委員会の理事会、経営会議には都も正式なメンバーとなっており、小池知事におかれては、是非、本日の情報も踏まえ、「環境最先端都市」東京でのオリンピックとして、恥ずかしくない環境対策、持続可能性に向けた対策を実現して頂けるよう、益々のリーダーシップを発揮していただきたいと強く念じております。
嬉しいことに、組織委員会の持続可能性部、内閣官房や環境省の方々、そして東京都のご担当セクションも来場。関係各位、一致団結して持続可能性への取組みに邁進して頂きたいと願っております。
生命力
06.26
先週、高齢の父が脳梗塞で倒れ救急車のお世話になった。父に付き添い、救急車
に乗るのはこれで2回目。
思えば、一昨年の検診で胃癌が発覚した後、昨年正月の胃と腎臓の摘出を皮切り
に、ヘルペス性顔面麻痺、心不全、食道癌、脳梗塞と、病気のオンパレード。す
べて老化とともに発症リスクが高くなるという病だが、なにもこんなに集中して
やって来なくても。。。介護する家族が疲弊する。
兎に角、この半年近くは仕事もめまぐるしく、加えて育児と親の世話とで忙殺さ
れまくっている。多方面に不義理をしてしまっているし、ブログなども書いてい
る余裕ゼロ。と言い訳もしつつ。。。(^^;)
翻って本人は、そんな家族の苦労などどこ吹く風で、様々な病名の下の入院の度
に、それぞれを克服して無事帰宅。
彼は今年78才になるが、20年前54才であっけなくあの世に逝ってしまった母にそ
の半分でも分けてあげて欲しかったと思うくらい、すこぶる生命力を感じる。
生命力の違い、何から来るのか?
「気にしない」ことだ。
父は昔から、なんというか解脱しているような所が有り、
「人は死んだら無になる。だから自分がやりたいように心地良く生きる。」
という信念の下我を貫いてきた。そして最近は更に強情に拍車がかかっており、
周りは苦労が絶えないが。。。(^_^;)??
私の座右の銘は「人生あっという間」。
子どもの頃に、とても仲の良かった兄を亡くして以来、身近な死を多数経験して
きており「人生は儚く、死んだらお終い」ということを日常的に意識させられて
きた。そのためか、私自身も、妙なプライドや外聞に囚われて、本来やりたいこ
とを我慢したり身動きがとれなくなったりという、周囲で見聞きする現象に陥る
ことがきわめて少ない。
正に人生を達観しているという自負がある。
んん?これって、遺伝子のなせる技?
お陰様で父は今回も意識が戻り、集中治療室には居るももの、今日も元気に過
ごしている。さすがの生命力!
私もこれを引き継いでいるに違いない。。。(^^)















